
SUCCESS CASE 成功事例&インタビュー EC運用22年の歴史から学ぶ、持続可能な「ファン作り戦略」

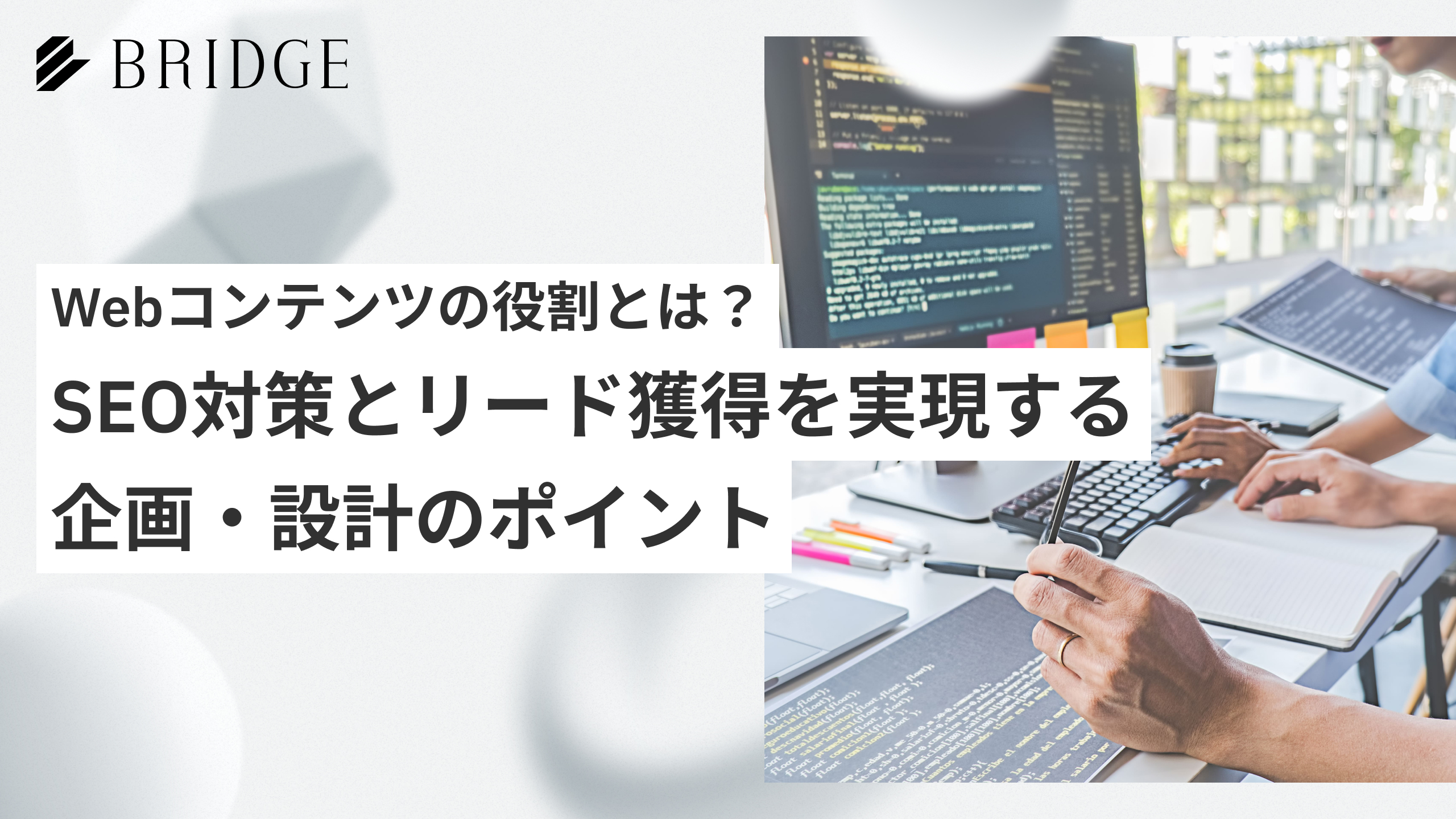
近年、多くの企業がコンテンツマーケティングの重要性を認識し、その戦略構築に力を入れています。
しかし、Webコンテンツを活用したプロモーションや集客で成果を出すためには、質の高いコンテンツを制作し、顧客ニーズに的確に応えることが不可欠です。
本記事では、「そもそもWebコンテンツとは何か?」という基本的な疑問から、Webコンテンツ作成の必要性、そして具体的な制作の流れまでを分かりやすく解説します。
1:Webコンテンツとは
-Webコンテンツの意味
-Webコンテンツの種類
2:Webコンテンツが必要な3つの理由
3:Webコンテンツ作成のフロー
-Webコンテンツの目的・発信するターゲット・ゴールを明確にする
-ユーザーが求めている情報を整理する
-導線を設計する
-制作体制を整える
-制作を依頼する
4:まとめ
「コンテンツ」という言葉は、本来「内容」や「中身」といった意味を持つ、非常に広範な言葉です。しかし、「Webコンテンツ」という言葉を使う場合、Webサイト上に存在するテキスト情報、画像、動画など、訪問者に提供されるあらゆる情報を指します。
Webコンテンツは、コンテンツ掲載者(Webサイトを運営する企業)と訪問者(Webサイトを閲覧するユーザー)がコミュニケーションを取るための重要な手段です。
現代において、ユーザーは様々なWebコンテンツを通じて企業を知り、競合他社と比較検討し、購買やサービス利用に至ります。そのため、Webコンテンツはビジネスにおいて非常に重要な要素となっています。
Webコンテンツには、記事、診断コンテンツ、ホワイトペーパー、SNS投稿など、様々な種類があります。それぞれの特徴をご紹介します。
オウンドメディアやブログなどで提供される、文章を主体としたコンテンツです。
お役立ち情報、最新情報、まとめ情報、インタビュー、事例紹介など、多様な形式があります。
達成したい目的に合わせて適切な記事を作成することが重要です。
記事はWebサイトに蓄積され、ターゲットユーザーにとって有益な情報であればあるほど、長期的な需要が見込めるコンテンツとなります。
ユーザーに適した商材を提案したり、Webサイトの回遊率を向上させたりする効果があります。
ユーザーは、心理テストや占いのように楽しみながら、自分に最適な情報を効率的に得ることができます。
診断結果がSNSでシェアされやすく、認知拡大にも繋がりやすいという特徴があります。
自社の商品やサービスを効果的にアピールするための資料として、Web上でダウンロードできる形式で提供されます。
ダウンロードの際にユーザーの氏名やメールアドレスなどの個人情報を取得できるため、メールマガジン配信など、ダイレクトなアプローチに繋げることができます。
Twitter、Facebook、InstagramなどのSNSを通じて、ユーザーは情報を得るようになっています。
SNS投稿と自社Webサイトを連動させ、ブランディング戦略の一環として活用する企業が増えています。
各種SNSによって特徴やユーザー層が異なるため、ユーザー層に合わせて使い分けることで、より効果的にSNSを活用することができます。
検索エンジンは、ユーザーにとって「有益なコンテンツ」を検索結果の上位に表示します。
質の高いWebコンテンツは、SNSなどでシェアされやすく、多くのアクセスと被リンクを獲得することで、検索順位の上位表示に繋がります。
既存の営業活動やWebサイトのコンテンツではアプローチできない潜在顧客(リード)に対し、新しいWebコンテンツを作成することで、将来的に自社の商品やサービスを購入する可能性のある見込み顧客にアプローチできます。
アプローチできたリードの様々なニーズに対し、適切なタイミングで興味を引く情報を提供することで、最終的に自社の商品・サービスを繰り返し購入してもらう顧客へと育成することができます。
ここでは、一例としてショッピングサイトの『特集ページ』に焦点を当ててご説明いたします。
例えば、ショッピングサイトへ訪れた時。
欲しい商品が決まっているユーザーは、価格や送料などの情報だけで購入を決定するかもしれません。
しかし、どの商品が良いか迷っているユーザーや、商品によってどのように課題を解決できるかを知りたいユーザーにとって、商品のスペック情報だけで購買意欲を高め、購入まで導くことができるのでしょうか。
同系統の商品で機能の比較検討であったり、その商品はどういうシーンで使うと効果的なのか、といった付加情報があれば、よりユーザーの購買モチベーションも高まるのではないかと思います。
ユーザーに付加情報を与えるための最も効果的な手段がwebコンテンツです。ただし、単純に商品訴求をした企業目線のコンテンツを作れば良いという訳でもありません。ユーザーのあらゆる二ーズをしっかりとキャッチして、購買意欲の上がる内容を、もっとも効果的なタイミングで発信することが重要なのです。
次に、Webコンテンツ作成の流れを順番に説明します。
この手順に沿って進めることで、コンバージョンにつながりやすいWebコンテンツを作ることができます。以下のポイントをしっかり押さえていきましょう。
Webコンテンツを作成する前に、まず「何のために」コンテンツを作るのかを明確にしましょう。 売上向上、見込み客獲得、ブランド認知拡大など、目的によってコンテンツの内容は大きく変わります。
例えば、新商品の認知度を高めたいなら、商品の特徴やメリットを分かりやすく伝えるコンテンツが必要です。 既存顧客の満足度を高めたいなら、商品の使い方や活用事例を紹介するコンテンツが効果的です。
コンテンツ制作のコンセプトをしっかりと固めておかないと、後々内容を詰めていくうちにブレかねないので、ここをきっちりと決めておくことが重要です。
誰にコンテンツを届けたいのか?ターゲットを明確にすることで、コンテンツの内容はより具体的になります。
ターゲットが「すでに自社の商品を購入したことがある人」なのか、「興味はあるけどまだ購入していない人」なのかによっても、コンテンツ内容は変わります。 顧客のニーズを徹底的に調査し、ペルソナに刺さるコンテンツを作成しましょう。
Webコンテンツ制作の際には、最終的にユーザーにどうなってもらいたいのかを設定することが欠かせません。ゴール設定は、コンテンツの効果を検証するための指標にもなります。
たとえば、商品購入を目指す場合、最初のゴールはその購入を促進することです。しかし、初回の購入が難しい場合、まずは訪問数の増加や、購入の一歩手前である問い合わせの増加をゴールに設定することができます。さらに、ユーザーをリピーターにするために、メルマガ登録やSNSでのシェアを目指すことも可能です。
ゴールを明確にすることで、コンテンツ制作の方向性が定まり、ユーザーの行動を促しやすくなります。
ユーザーがコンテンツを検索している理由を理解することが重要です。ユーザーは、自分の悩みを解決するために情報を探しているのか、すでに商品やサービスを知っており、競合と比較しているのか、あるいは購入を決定するために後押しが必要なのか、購買欲求の段階によって提供すべき情報が異なります。
ゴール設定が商品購入であったとしても、ユーザーのモチベーションによって訴求すべき内容が変わるため、ターゲットに合わせたアプローチが求められます。
Webコンテンツを作っただけでは意味がありません。ユーザーにコンテンツを見てもらわなければ、効果を発揮することができません。ここで大切なのは、導線設計です。
潜在欲求ユーザー(悩みはあるが解決策がわからない)には、悩みを連想させるキーワードで広告やSNS広告を出して気づきを与えることが有効です。これにより、ユーザーがより詳しく知りたいと思い、クリック繋がります。
一方で、顕在欲求ユーザー(自分に必要なものを探している)は、商品名やカテゴリ名でのリスティング広告や、サイトを訪れたことがあるユーザーに対しては、リマーケティング広告やSNS広告での再アプローチが効果的です。
SEO対策を施したコンテンツを適切なタイミングで届けることが、コンテンツの成功に大きく影響します。
Webコンテンツ作成時には、訴求方法をしっかり考えましょう。どのようなキャッチコピーやストーリーでゴールに導くか、ターゲットに最適な表現方法を選ぶことが大切です。
Webコンテンツの形式には、文章だけでなく、画像や音声、動画などもあります。複雑な内容を説明する際には、図表やイラストを挿入することで、より理解しやすくなります。
例えば、技術的なコンテンツの場合、文章だけでなく、動画を使って解説することで、ユーザーにとっての分かりやすさが格段に向上します。
また、コンテンツのターゲットリテラシー(知識レベル)を意識し、初心者向けの場合は簡単な表現を、専門家向けには詳細な情報を提供することで、効果的な訴求が可能になります。
WebコンテンツのSEOを考慮すると、ユーザーが継続的に訪問し、閲覧できる情報を提供することが非常に重要です。質の高いコンテンツが蓄積されることで、顧客の信頼感が増し、集客に繋がります。そのため、効率的にWebコンテンツを生産していくために、コンテンツの「型」を事前に作成し、パターン化する方法が有効です。コンテンツの型を用意しておけば、各記事が一定の基準を満たし、質の高いコンテンツが作りやすくなります。
また、良質なコンテンツを提供し続けるには、制作環境の整備も欠かせません。特に近年では、多くの開発ツールやコンテンツ管理システム(CMS)が登場し、ホームページ制作の知識がなくても、簡単にオウンドメディアを構築できるようになっています。例えば、CMSを活用すれば、豊富なテンプレートからデザインを選ぶことができ、コンテンツを一元管理して業務時間を大幅に短縮できます。これにより、制作スタッフの負担を軽減し、効率よくコンテンツを更新できます。
Webコンテンツの内容、表現方法が決まり、コンテンツの骨子が完成したら、それをもとにライターやコンテンツ制作スタッフに提示して制作に取り掛かります。この段階で重要なのは、企画者と制作者の間で完成イメージを共有することです。特に、企画者と制作者が異なる場合は、双方で意図のズレが生じないように注意が必要です。
コンテンツの骨子だけではなく、コンテンツのコンセプトや目的、ターゲットなども詳しく共有することで、制作者はより具体的にコンテンツを作成できます。これにより、コンテンツが目的に沿ったものとなり、効果的にターゲットにアプローチすることが可能です。
さらに、ライターの作業を効率化し、コンテンツの表現方法を統一することも重要です。例えば、文体(です・ます調)や数字の表記ルール、改行の使い方、禁止する表現など、ライティングに関する基本ルールをマニュアル化して統一することで、ライターは迷うことなく作業を進められます。このように統一されたガイドラインを守ることで、ライターによって文章にバラつきが生じることを防ぎ、品質の安定が図れます。
コンテンツが納品された後は、企画者が最終確認を行いましょう。誤字や脱字、または企画者の意図がライターにうまく伝わらなかった部分がないかをチェックします。場合によっては、コンテンツに加筆や修正が必要となることがあります。最終的に、ユーザーにとって「有益なWebコンテンツ」と認識されるよう、こだわりを持ってコンテンツを仕上げていきましょう。
SEOを意識してWebコンテンツを作成する際は、以下のポイントも意識しましょう。
これらの対策を意識し、Webコンテンツを作成することで、SEO効果が高まり、より多くのユーザーにアプローチできるようになります。
Webコンテンツ作成を難しく考えているご担当様も多いかと思いますが、まずは、あなたのWebサイトの現状を分析し、どのステップから改善が必要かを見極めてみましょう。
そして、今日からできる小さな一歩、例えば「ターゲットとする顧客像(ペルソナ)を具体的に書き出してみる」ことから始めてみませんか? 効果的なWebコンテンツは、あなたのビジネスを成長させる強力な武器になります。
大阪に拠点を持つ株式会社ブリッジコーポレーションは、単なるWebサイト制作にとどまらず、ターゲットに響くデザインやコンテンツ設計を重視し、コンバージョンにつながるWebサイトを構築します。
公開後も、アクセス状況やユーザーの動向を分析し、効果的な改善策を提案することで、継続的な成長をサポートします。
Webコンテンツ制作でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。